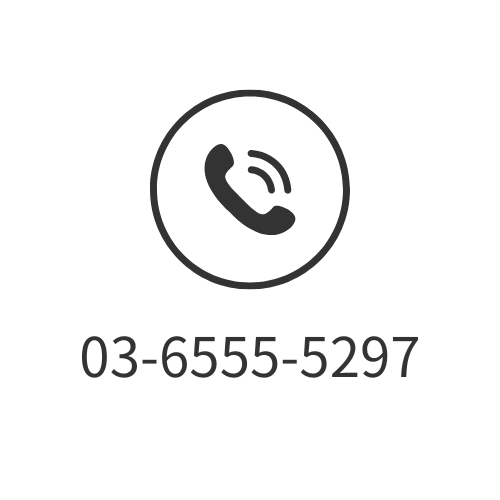品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
契約期間
労働基準法14条1項柱書
労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
| 契約期間の制限 | 任意退職 | ||
|---|---|---|---|
| 期間の定めのないもの | 任意退職(民法) | ||
| 期間の定めのあるもの | 下記以外の者に係るもの | 3年 (更新後も3年) | (労働基準法第137条)
|
| 一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの | 上限なし | ただし、「やむを得ない事由」がある場合は、いつでも退職することができます。(民法第628条) | |
| 高度の専門的知識等を有する労働者に対する労働契約 | 5年 (更新後も5年) | ||
| 満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約 | 5年 (更新後も5年) | ||
一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの
- 「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」には、契約期間の上限の定めはない。(法14条1項)
- 「一定の事業の完了に必要な期間を定めるもの」とは、例えば5年間で完了する土木工事においては、技師を5年間の契約で雇い入れる場合のように、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合を指すため、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要である。
| 専門的知識等 | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 博士の学位を有する者 | ||
| 2 | 次に掲げるいずれかの資格を有する者 | イ. 公認会計士 ロ. 医師 ハ. 歯科医師 ニ. 獣医師 ホ. 弁護士 ヘ. 1級建築士 ト. 税理士 チ. 薬剤師 リ. 社会保険労務士 ヌ. 不動産鑑定士 ル. 技術士 ヲ. 弁理士 | |
| 3 | ITストラテジスト試験若しくはシステムアナリスト試験またはアクチュアリーに関する資格試験に合格した者 | ||
| 4 | 特許法に規定する特許発明の発明者、意匠法に規定する登録意匠を創作した者または種苗法に規定する登録品種を育成した者 | ||
| 5 | 次のいずれかに該当する者であって、労働契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる賃金の額を1年当たりの額に換算した額が1,075万円を下回らないもの | イ. 農林水産業の技術者、鉱工業の技術者、機械・電気技術者、建築・土木技術者、システムエンジニア、デザイナーの業務に就こうとする者であって、一定の実務経験などを有するもの ロ. 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握またはそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務に就こうとする者であって、システムエンジニアの業務に5年以上従事した経験を有するもの | |
| 高度の専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約(上限5年) | 次のいすれかに該当する者であって、労慟契約の期間中に支払われることが確実に見込まれる貸金の額を1年当たりの額に操算した額が1,075万円を下回らないもの
| |
|---|---|---|
| 高度プロフェッショナル制度 | 労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与顧の3倍の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額(1,075万円)以上であること。 | |
| 無期転換ルールの特例 (無期転換申込権発生の除外) | 5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く専門的知識等を有する有期雇用労働者(注) については、無期転換申込権が発生しない。 (注)事業主との間で締結された有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われると見込まれるた有期労働契約の契約期間に当該事業主から支払われると見込まれる賃金の額を1年間当たりの賃金の額に換算した額が厚生労働省令で定める額(1,075万円)以上であって、当該専門的知識等を必要とする業務に就くものに限る | |
満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約
満60歳以上の労働者との間には、5年以内の契約期間の労働契約を締結することができる。(法14条1項2号)
参照 高年齢者の安定した雇用の確保の促進
定年を定める場合の年齢
事業主が定年の定めをする場合には、当該定年は、「60歳」を下回ることができない。
ただし、当該事業主が雇用する労働者のうち、高年齢者が従事することが困難であると認められる業務として厚生労働省令で定める業務(「坑内作業」の業務)に従事している労働者については、この限りでない。(高年齢者雇用安定法8条、則4条の2)
- 罰則の適用はありません。
上限期間を超える期間を定めた労働契約
(平成15年10月22日基発1022001号)
法14条に規定する上限期間を超える期間を定めた労働契約を締結した場合は、法14条1項違反となり、当該労働契約の期間は、
1項1号(専門的知識などであって高度のものとの労働契約)または2号(満60歳以上の労働者との労働契約)に該当するものについては5年、
その他のものについては3年となる。
労働基準法には、規範的効力(=強行的効力+直律的効力)が与えられているため、上記の扱いとなります。
「労働契約そのものが無効になる」わけでも、「期間の定めのない労働契約となる」わけでもありません。
有期労働契約の任意退職
一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、1年を超える期間の定めのある労働契約を締結した労働者(契約期間の上限が5年とされている者を除く)は、当該労働契約の期間の初日から1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができる。(附則137条)
「1年を超える期間の労働契約」を締結した労働者は、1年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職することができますが、この場合であっても、
①「一定の事業の完了に必要な期間を定めて労働する労働者」、
②契約期間の上限が5年とされている者(「高度の専門的知識等を有する労働者」、「60歳以上の労働者」)は、
退職の申出をすることはできません。
民法628条
当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
第1条(有期労働契約の変更等に際して更新上限を定める場合等の理由の説明)
使用者は、期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)の締結後、当該有期労働契約の変更又は更新に際して、通算契約期間(労働契約法第18条第1項に規定する通算契約期間をいう。)又は有期労働契約の更新回数について、上限を定め(=最初の契約締結より後に更新上限を新たに設けるケース)、又はこれを引き下げよう(=最初の契約締結のときに設けていた更新上限を短縮するケース)とするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明しなければならない。
⇨ 参照 5条 無期転換後の労働条件に関する説明
第2条(雇止めの予告)
使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、又は雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければならない。
第3条(雇止めの理由の明示)
- 前条の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
- 有期労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しなかった理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。
第4条(契約期間についての配慮)
使用者は、有期労働契約(当該契約を1回以上更新し、かつ、雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限る。)を更新しようとする場合においては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努めなければならない。
第5条(無期転換後の労働条件に関する説明)
使用者は、労働基準法第15条第1項の規定により、労働者に対して労働基準法施行規則第5条第5項に規定する事項を明示する場合においては、当該事項(同条第1項各号に掲げるものを除く。)に関する定めをするに当たって労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえて就業の実態に応じて均衡を考慮した事項について、当該労働者に説明するよう努めなければならない。
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索
サイドメニュー
- Between Japan and Nepal
- Tokutei Ginou
- QandA
- Shop info
- English