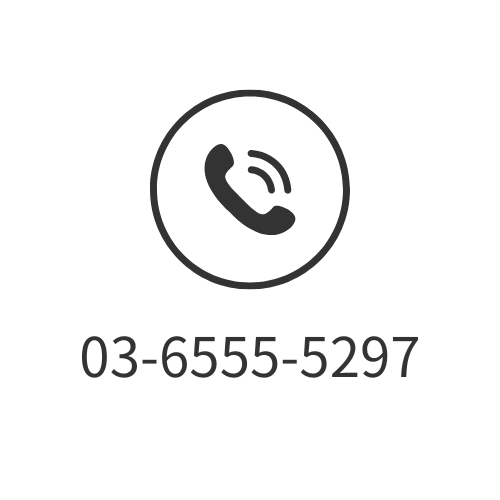品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
徴収法
一般保険料率
労働保険は、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険の総称です。事業主は、これら2つの保険の保険料を、原則として一体的に申告・納付します。この際に用いるのが「一般保険料率」です。
目 次
労災保険率の決定
- 労災保険率は、労災保険法の規定による保険給付及び社会復帰促進等事業に要する費用の予想額に照らし、将来にわたって、労災保険の事業に係る財政の均衡を保つことができるものでなければならない。(法12条2項)
- 「労災保険率」は、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、労災保険法の適用を受けるすべての事業の「過去3年間の業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の災害率」並びに「二次健康診断等給付に要した費用の額」、「社会復帰促進等事業として行う事業の種類及び内容」その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める。(法12条2項)
- 「特別加入者に係る保険給付に要した費用の額」は該当しません。
- 「雇用保険率」の決定の規定ではありません。
労災保険率
- 労災保険率は「事業の種類」によって異なり、それぞれの業種の過去3年間の災害率その他事情を考慮して改定される。(則16条、則別表第1)
-
かつては、5年間でしたが、災害率の推移にできるだけ即応しうるように、昭和40年改正により、3年間に短縮されました。
労災保険率の改定は必ずしも3年ごととは限りません。平成21年度、平成24年度、平成27年度、平成30年度と改定されてきましたが、令和3年度は、据え置きとされました。 -
令和6年度の労災保険率は、改定が行われました。
-
「事業の規模」ごとに定められているのではありません。
-
- 労災保険率は、労働保険徴収法施行規則で定める事業の種類ごとに定められており、その最高は、1,000分の88(注)であり、その最低は、1,000分の2.5(「金融業、保険業または不動産業」など)である。(則別表第1)
- (注)金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業またはドロマイト鉱業を除く)または石炭鉱業
- 労災保険率の最高は「1,000分の100」を超えていません。
- 労災保険率には、すべての事業において、一律1,000分の0.6の非業務災害率(複数業務要因災害に係る災害率、通勤災害に係る災害率、二次健康診断等給付に要した費用の額その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める率)が含まれている。(法12条3項、則16条2項)
- 事業主が同一人であるが、業種が異なる2以上の部門が場所的に分かれて独立した運営が行われている場合には、それぞれ別個の事業として取り扱われ、それぞれ異なる業種に応ずる労災保険率が適用される。(平成28年2月29日基発0229第2号)
- 労働者派遣事業における事業の種類は、派遣労働者の「派遣先」での作業実態に基づき決定する。派遣労働者の派遣先での作業実態が数種にわたる場合には、主たる作業実態に基づき事業の種類を決定することとし、その場合の主たる作業実態は、それぞれの作業に従事する派遣労働者の数、当該派遣労働者に係る賃金総額などにより判断する。(平成28年2月29日基発0229第2号)
- 派遣労働者に対して、派遣会社の労災保険率(その他の各種事業、1,000分の3)を適用することは、実態にそぐわないことになります。なお、雇用保険率は、原則として、「一般の事業」の雇用保険率となります。
| 事業の種類 | 令和7年度雇用保険 | 令和6年度雇用保険率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 雇用保険率 |
|
| ||||
| 1 | 一般の事業 | 1,000分の14.5 |
|
| 1,000分の15.5 | |
|
|
| ||||
| 二事業に係る率 |
|
|
| |||
| 2 | 農林水産業、清酒製造業 | 1,000分の16.5 |
|
| 1,000分の17.5 | |
|
|
| ||||
| 二事業に係る率 |
|
|
| |||
| 3 | 建設の事業 | 1,000分の17.5 |
|
| 1,000分の18.5 | |
|
|
| ||||
| 二事業に係る率 |
|
|
| |||
- 事業の種類ごとに細かく設定されている労災保険率とは異なり、一般の事業の雇用保険率は一律に同一の率となります。例えば、「金融業」も「金属鉱業」も同じ率となります。
- 農林水産業、清酒製造業、建設の事業については、短期雇用特例被保険者が多く雇用される実態に鑑み、社会的公平の見地から、別に雇用保険率が設定されています。
- 建設業については、建設労働者雇用改善法に基づく建設労働者の福祉等に関する事業等を雇用保険の能力開発事業として行う費用に充てるため他の事業より1,000分の1多くなっています。
- 「一般の事業以外の事業」を、特に「特掲事業」といいます。
| 1+2+3=雇用保険率 | |||
| 1 | 失業等給付費等充当徴収保険率 | 1,000分の8 特掲事業(注)については、1,000分の10とし、変更されたときは、その変更された率とする
| 「失業等給付費等充当徴収保険率」とは、雇用保険率のうち失業等給付及び就職支援法事業に要する費用に対応する部分の率をいいます。(法12条4項1号かっこ書) |
| 2 | 育児休業給付費充当徴収保険率 | 1,000分の5 (変更されたときは、その変更された率とする) | 「育児休業給付費充当徴収保険率」とは、雇用保険率のうち育児休業給付に要する費用に対応する部分の率をいいます。(法12条4項2号かっこ書) |
| 3 | 二事業費充当徴収保険率 | 1,000分の3.5 (上記3.建設業については、1,000分の4.5とし、変更されたときは、その変更された率とする) | 「二事業費充当徴収保険率」とは、雇用保険率のうち雇用安定事業及び能力開発事業(就職支援法事業以外の能力開発事業に限る)に要する費用に対応する部分の率をいいます。(法12条4項3号かっこ書) |
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索