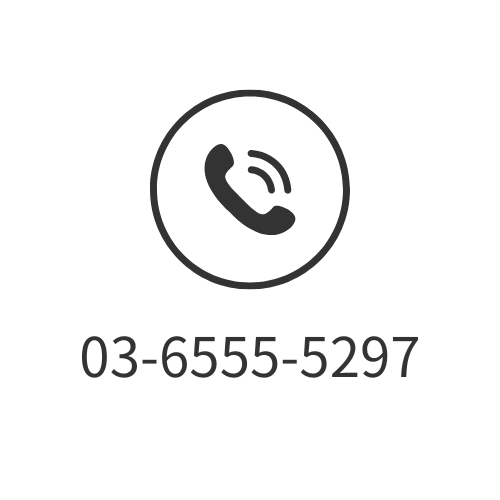出向(在籍出向) は現在の企業との雇用関係を維持したまま, 他企業の業務に従事するものです。出向元と労働者との間にも雇用関係(労働契約) が存在しており、①労働者と出向元との間及び②労働者と出向先との間で雇用関係が併存している状態です 。
(平成24年8月10日基発0810第2号)
在籍出向とは使用者(出向元)と出向を命じられた労働者との間の労働契約関係が終了することなく、出向を命じられた労働者が出向先に使用されて労働に従事することをいいます。
出向を実現するためには、まず、出向元と出向先との間において従業員の受け入れについての出向契約の締結が必要です。
労働者の同意ついて
当初の労働契約の相手方とは別の企業に対して労務を提供するものであるため、 労働契約上の地位の一部を第三者に譲渡するものとして、 労働者の同意が必要となります(民法625条1項)。
(最判平15・4・18労判八四七・一四〈新日本製鐵事件〉)
ある事業場における①特定の業務を協力会社である別会社に業務委託するに伴いその委託された業務に従事していた労働者に出向が命じられた場合において②入社時及び出向発令時の就業規則に社外勤務条項(出向条項)があり、また当該労働者に適用される労働協約にも同様の社外勤務条項(出向条項)があり③さらに労働協約である社外勤務協定において、出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられていたという事情の下では、会社は労働者の個別的同意なしに出向を命じることができる。
出向は、その期間が長期化した場合でも、出向元との労働契約関係の存続自体が形骸化していなければ、直ちに転籍と同視して個別的同意を要するとまではいえない。当初三年間の出向を三度にわたり延長する本件出向延長措置には合理性があり、これにより労働者が著しい不利益を受けるものともいえないので権利濫用とはいえない。
(名古屋地判昭55・3・26労民三一・二・三七二〈興和事件〉)
採用時に労働者が、将来特定の関連会社への出向が社内配転と同様になされ得るとの説明を受けこれに同意した場合、右同意が労働者の十分な理解の下でなした真意に基づくものであり、内容が著しく不利益であるとか将来不利益を招くことが明白であるとの事情のない限り、会社はかかる入社時の包括的同意により出向命令権限を取得する。
出向中の労働関係について
(昭和61年6月6日基発333号)
在籍型出向の出向労働者については、出向元及び出向先の双方とそれぞれ労働契約関係があるので、出向元及び出向先に対しては、それぞれ労働契約関係が存する限度で労働基準法の適用がある。
すなわち、出向元、出向先及び出向労働者三者間の取決めによって定められた権限と責任に応じて出向元の使用者又は出向先の使用者が出向労働者について労働基準法における使用者としての責任を負う。
労働者が出向する場合については、 労働者と出向先との間で新たに雇用関係 (出向労働関係) が成立するものであるため、 出向に際して出向先は、 労働基準法15条1項、 労働基準法施行規則5条に基づき当該事業場における労働条件を明示することが必要であるというのが行政見解です。この労働条件の明示は、出向元が出向先のために代わって行うことも差し支えないものとされています。
出向元の就業規則のうち労務提供を前提としない部分につては依然として適用を受け続けます。
その一方、出向先が指揮命令を行うため、出向先の勤務管理や服務規律に服することになります。
給与・手当・賞与の支払いを出向先が行うか出向元が行うかについては、両社間の出向契約によって確定されます。