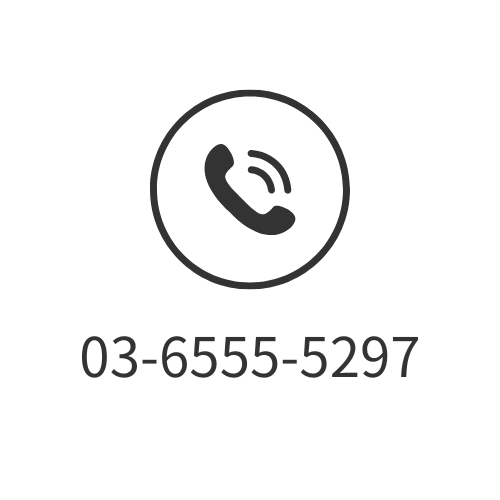品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
(メリット)収支率
継続事業(一括有期事業を含む)のメリット制の適用を受けるためには、連続する3保険年度の間における第1種調整率を用いて算定した「(メリット)収支率」が100分の85を超え、または100分の75以下でなければならない。(法12条3項)
- 収支率を判断する算定期間を長くするほど収支率の安定性は増しますが、災害発生状況の推移を速やかに反映させるという点とバランスをとって、3年とされています。
目 次
メリット制
- メリット制の適用対象となる事業
- (メリット)収支率 本ページ
| (メリット)収支率 | ||
| 分子 | / | 分母 |
| 基準日以前3保険年度間の業務災害に関する「保険給付の額+特別支給金の額」 | 基準日以前3保険年度間の | |
簡単にいうと、「(メリット)収支率」とは、政府からみた、収入(保険料収入)に対する支出(保険給付の額)の割合のことです。
| メリット収支率の算定基礎から除かれるもの(及びこれに付随する特別支給金) | ||
|---|---|---|
|
| 区分 | 除かれる理由 |
| 1 | 失権差額一時金
| 本来の年金給付が消滅したことに伴う「補てん」であり、実際の事業場の災害状況とは直接関係がないため
|
| 2 | 障害補償年金差額一時金 | 年金の支給事由変更に伴う「調整給付」であり、新規災害発生に由来しないため |
| 3 | 特定疾病にかかった者に係る保険給付 | 疾病の責任を最終事業場の事業主だけに負わせることは適当ではないため
|
| 4 | 通勤災害に係る保険給付 | 通勤災害は、事業主の業務遂行や安全管理体制に左右されるものではないため |
| 5 | 二次健康診断等給付に係る保険給付 | 災害の発生に直接結び付くものではないため、事業主の災害防止努力を反映しないため |
| 6 | 第3種特別加入者のうち、海外派遣者の特別加入に係る事業により業務災害が生じた場合に係る保険給付 | 国内の事業場の労働条件や安全管理状況を反映するものではないため
|
| 7 | 複数事業労働者の非災害発生事業場における賃金額に係るもの | 災害を発生させていない事業場の賃金分であるため |
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索