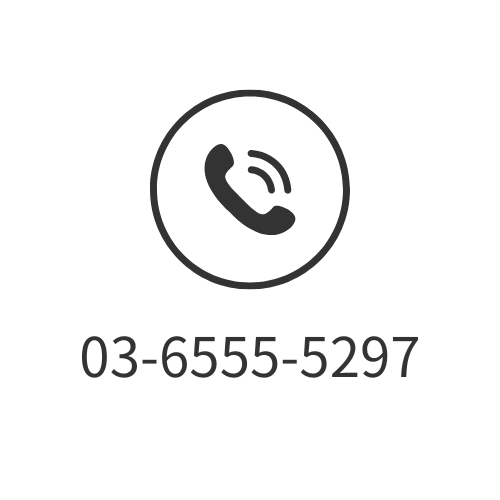品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
労災保険法
遺族(補償)年金
遺族(補償)等年金は、お亡くなりになった方の収入によって生計を維持していた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹のうち最先順位者が受け取れますが、妻以外の遺族については、労働者の死亡の当時に一定の高齢又は年少であるか、あるいは一定の障害の状態にあることが必要です。
目 次
遺族給付
| 遺族(補償)等年金 | 遺族(補償)等一時金 (法16条の7、法22条の4第3項) | 遺族(補償)等年金差額一時金 最低限の額の受け取り前に死亡 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 順位 | 遺族 | 生計維持 生計同一 | 年齢 | その他 | 順位 | 遺族 | 生計維持 | 遺族 | 生計同一 主として「同じ屋根の下の家族」 |
| 1 | 妻 | 〇 | 1 | 配偶 | 生計維持関係に関わらず 最先順位者 | 配偶 | 〇 | ||
| 夫 | 〇 | 60歳以上 | もしくは 障害 | 2 | 子 | 〇 | 子 | 〇 | |
| 2 | 子 | 〇 | 18歳年度末まで | もしくは 障害 | 父母 | 〇 | 父母 | 〇 | |
| 3 | 父母 | 〇 | 60歳以上 | もしくは 障害 | 孫 | 〇 | 孫 | 〇 | |
| 4 | 孫 | 〇 | 18歳年度末まで | もしくは 障害 | 祖 | 〇 | 祖 | 〇 | |
| 5 | 祖 | 〇 | 60歳以上 | もしくは 障害 | 兄 | 〇 | |||
| 6 | 兄 | 〇 | 18歳年度末まで/60歳以上 | もしくは 障害 | 配偶 | ||||
| 7 | 夫 | 〇 | 55歳以上 | 若年支給停止者 | 3 | 子 | 子 | ||
| 8 | 父母 | 〇 | 55歳以上 | 若年支給停止者 | 父母 | 父母 | |||
| 9 | 祖 | 〇 | 55歳以上 | 若年支給停止者 | 孫 | 孫 | |||
| 10 | 兄 | 〇 | 55歳以上 | 若年支給停止者 | 祖 | 祖 | |||
| 4 | 兄 | 生計維持関係に関わらず、最後順位者 | 兄 | ||||||
胎児であった子
- 労働者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、将来に向かって、その子は、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた子とみなされる。(法16条の2第2項、法22条の4第3項)
- 胎児であった子が出生したときは、労働者の死亡の当時「生計を維持していた」とみなされるにすぎないから、その子が厚生労働省令で定める障害の状態にあっても、「労働者の死亡の当時厚生労働省令で定める障害の状態」にあるとはみなされない。
- 胎児が障害の状態で出生した場合であっても、労働者の死亡の当時障害の状態にあったものとはみなされません。
- したがって、労働者の死亡の当時胎児であった子は、障害の状態にあっても、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときは受給権者ではなくなり、また、受給資格者でもなくなります。
生計を維持していた
- 労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたことの認定は、当該労働者との同居の事実の有無、当該労働者以外の扶養義務者の有無その他必要な事項を基礎として「厚生労働省労働基準局長」が定める基準によって行う。(則14条の4)
- (昭和41年10月22日基発1108号)
「労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた」ものについては、労働者の死亡の当時において、その収入によって日常の消費生活の全部または一部を営んでおり、死亡労働者の収入がなければ通常の生活水準を維持することが困難となるような関係(生計維持関係)が常態であったか否かにより判断する。
次のような場合には、生計維持関係が「常態であった」ものと認められます。- 業務外の疾病その他の事情により当該遺族との生計維持関係が失われていても、それが「一時的な事情によるもの」であることが明らかであるとき
- 生計維持関係開始直後において当該労働者が死亡した場合であっても、労働者が生存していたとすれば、特別の事情がない限り、生計維持関係の「継続性が推定し得る」とき
- 就職直後において死亡したため、その収入により当該遺族が生計を維持するに至らなかった場合であっても、労働者が生存していたとすれば、生計維持関係が「まもなく常態となるに至ったであろうことが明らか」であるとき
- 労働者の死亡の当時における当該遺族の生活水準が年齢、職業などの事情が類似する一般人のそれを著しく上回る場合を除き、当該遺族が死亡労働者の収入によって消費生活の全部または一部を営んでいた関係が認められる限り、当該遺族と死亡労働者との間に「生計維持関係」があったものとして差し支えない。(昭和41年10月22日基発1108号)
- 「生計を維持していた」とは、専ら、または主として労働者の収入によって生計を維持することを要せず、相互に収入の全部または一部をもって生計費の一部を共同計算している状態であれば足りる。例えば、共稼ぎの夫婦も配偶者の他方の収入の一部によって生計を維持していたことになる(収入要件)。
(昭和41年1月31日基発73号) - 「生計を維持していた」とは、生計同一 + 収入要件
労働者を故意に死亡させた者は、遺族(補償)給付を受けることができる遺族にはならない。(法16条の9第1項、法22条の4第3項)
- 過失は含みません。
労働者の死亡前に、当該労働者の死亡によって遺族(補償)年金を受けることができる先順位または同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族(補償)年金を受けることができる遺族とならない。(法16条の9第2項、法22条の4第3項)
- 「後順位」の遺族となるべき者を故意に死亡させても遺族からは排除されません。
遺族(補償)年金を受けることができる遺族が、遺族(補償)年金を受けることができる先順位または同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族(補償)年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族(補償)年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。
(法16条の9第4項、法22条の4第3項)
労災保険法16条の3、(法22条の4第3項)
遺族補償年金の額は、別表第1に規定する額とする。
| 遺族の数 「受給権者 + 受給権者と生計を同じくしている受給資格者(若年支給停止者を除く)」 | 遺族(補償)年金の額 |
|---|---|
| 1人 | 給付基礎日額の153日分 ただし、55歳以上の妻または厚生労働省令で定める障害の状態にある妻にあっては、給付基礎日額の175日分 |
| 2人 | 給付基礎日額の201日分 |
| 3人 | 給付基礎日額の223日分 |
| 4人以上 | 給付基礎日額の245日分 |
- 受給権者(労働者の子)と、受給権者と生計を同じくしている遺族(労働者の母)がいるような場合、遺族の数は2人となり、給付基礎日額の201日分が労働者の子に対して支給されます。
遺族(補償)年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、遺族(補償)年金の額は、別表第1に規定する額をその人数で除して得た額とする。
(法16条の3第2項、法22条の4第3項)
- 受給権者が3人おり、それぞれと生計を同じくしている受給資格者が合計3人いる場合、額の算定の基礎となる遺族の人数は合計で6人となり、受給権者1人あたりの遺族(補償)年金の額は、給付基礎日額の245日分相当額の「3分の1」の額となります。
所在不明による支給停止
遺族(補償)年金を受ける権利を有する者の所在が「1年以上」明らかでない場合には、当該遺族(補償)年金は、
- 同順位者があるときは同順位者の、
- 同順位者がないときは次順位者の申請によって、その所在が明らかでない間、その「所在不明となった」ときにさかのぼって、その支給が停止される。
- この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者が先順位者となる。(法16条の5第1項、法22条の4第3項)
- 受給権者が「所在不明となった」ときにさかのぼり、その月の翌月から支給が停止されます。
支給停止を解除したときは、その解除の月の翌月分から支給を再開すればよく、所在が明らかとなったときにさかのぼることを要しない。
(昭和41年1月31日基発73号)
失権
遺族(補償)年金の受給権は、受給権者が次のいずれかに該当するに至ったときは、消滅する。(法16条の4第1項、法22条の4第3項)
| 失権事由 |
|---|
|
- 遺族(補償)年金の受給権者が「再婚」により受給権を失った場合には、同一死亡労働者に関して、再び受給権者となることはありません。したがって、再婚相手と離婚をしたとしても再び受給権者となることはありません。
- 婚姻には、いわゆる内縁関係も含まれるため、正式に婚姻していない場合でも遺族(補償)年金の受給権を失うことがあります。
- 遺族(補償)年金には、遺族厚生年金に規定されている「若年期の妻の失権」はありません。
受給権者が失権した場合の取扱い
| 受給権者の失権後の状況 | 該当者の有無 | 取扱い内容 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 同順位者がいる | あり | 額の改定 | 遺族の人数が減少するため、給付額を再計算する |
| 後順位者がいる | あり | 転給 | 受給権が後順位者に移転する |
補足(理解のポイント)
- 同順位者あり
→ 受給権はそのまま存続し、人数変更による金額調整が行われる。
-
後順位者あり
→ 先順位者の受給権が消滅し、新たに後順位者が受給権者となる。
直系血族又は直系姻族以外の者の養子
直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったときは、遺族(補償)年金の受給権は消滅する。(法16条の4第1項3号、法22条の4第3項)
子の受給権は、
- 「直系血族又は直系姻族以外」の養子になった場合は失権しますが、
- 「直系血族又は直系姻族」の養子になっても失権することはありません。
- 妻が持っていた遺族(補償)年金の受給権が妻の再婚により失権し
- 子に受給権が転給された後
- 子1人では生活ができないため、直系血族である祖父(死亡した父の父)の養子になっても子が失権することはありません。
「直系血族又は直系姻族以外の養子」となったときに失権するのは、死亡に関する保険給付
- 労災保険法での遺族(補償)等年金
- 国民年金法での遺族基礎年金
- 厚生年金保険法での遺族厚生年金においての共通ルールです。
養子には、「事実上養子縁組と同様の事情にある者」も含まれます。
なお、「事実上の養子縁組関係」とは、主として未成年の受給権者が傍系尊属その他の者によって扶養される状態があり、かつ、扶養者との間に養親又は養子と認められる事実関係を成立させようとする合意がある場合のことを指します。(昭和41年1月31日基発73号)
遺族(補償)年金前払一時金の請求
当分の間、労働者が業務上の事由又は通勤により死亡した場合における当該死亡に関しては、遺族(補償)年金を受ける権利を有する遺族に対し、その請求に基づき、保険給付として、遺族(補償)年金前払一時金が支給される。(附則60条1項、附則63条1項)
- 一家の支柱である労働者が死亡した場合に、残された遺族が生業を営むための資金、独立安定した経済状態に至るまでの資金等としてまとまった額の給付を行うため、又、一時金による支給を希望する声が多いため、「遺族(補償)年金前払制度」が設けられています。
遺族(補償)年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回に限り行うことができる。(則附則33項、則附則50項、則附則27項)
- 「若年支給停止者」であっても、遺族(補償)年金前払一時金の請求をすることができます
(政府は、労働条件の最低基準である労働基準法の災害補償については履行しなければならず、この災害補償に相当するものが前払一時金であるためです)。 - 転給により遺族(補償)年金の受給権者となった者であっても、失権した先順位者がすでに請求していない限り、遺族(補償)年金前払一時金の請求をすることができます。
遺族(補償)年金前払一時金の請求は、遺族(補償)年金の請求と同時に行わなければならない。(則附則33項、則附則50項、則附則26項)
ただし、遺族(補償)年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該遺族(補償)年金を請求した後においても遺族(補償)年金前払一時金を請求することができる。(則附則33項、則附則50項、則附則26項ただし書)
遺族(補償)年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。
(附則60条5項、附則63条3項)
- 遺族(補償)前払一時金は、支給決定通知日の翌日から起算して「1年以内」であれば、遺族(補償)年金を請求した後においても請求をすることができますが、遺族(補償)年金前払一時金の請求権の時効は、これを行使することができる時から「2年」です。
- 転給により遺族(補償)年金の受給権者となった者は、先順位者が遺族(補償)年金前払一時金の請求を既に行っていない場合には、遺族(補償)年金前払一時金の支給を請求することができます。
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索
サイドメニュー
- Between Japan and Nepal
- Tokutei Ginou
- QandA
- Shop info
- English