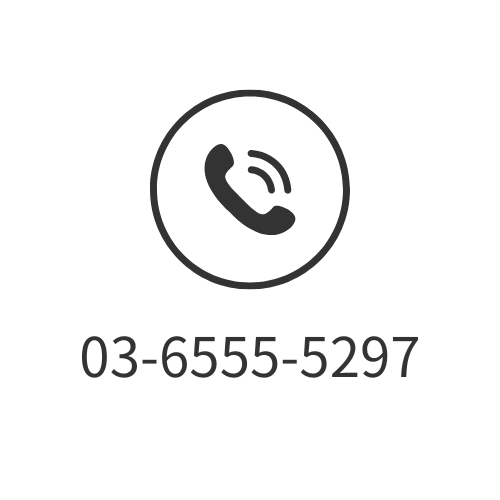品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
労災保険法
費用徴収
労災保険法における「費用徴収」とは、本来政府が負担する保険給付費用の全部または一部を、原因を作った事業主や不正受給者から徴収する制度です。
目 次
給付通則等
| 保険給付 | 限度 |
|---|---|
| 業務災害に関する保険給付 | 「労働基準法」の規定による災害補償の価額が限度
|
| 複数業務要因災害に関する保険給付 | 複数業務要因災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する「労働基準法」の規定による災害補償の価額(当該複数業務要因災害に係る事業ごとに算定した額に限る)が限度 |
| 通勤災害に関する保険給付 | 通勤災害を業務災害とみなした場合に支給されるべき業務災害に関する保険給付に相当する「労働基準法」の規定による災害補償の価額が限度 |
複数業務要因災害に係る費用徴収も、通勤災害の場合と同様に、仮に複数業務要因災害を業務災害とみなした場合の災害補償の価額(ただし、当該複数事業労働者を使用する事業ごとに算定した額に限る)の限度で行います。(令和2年8月21日基発0821第1号)
| 1 | 事業主が故意または重大な過失により保険関係成立届を提出していない期間中に生じた事故 |
|---|---|
| 2 | 事業主が一般保険料を納付しない期間(督促状に指定する期限後の期間に限る)中に生じた事故 |
| 3 | 事業主が故意または重大な過失により生じさせた業務災害の原因である事故 |
- 事業主からの費用徴収が行われる場合の徴収金の額は、厚生労働省労働基準局長が保険給付に要した費用、保険給付の種類、一般保険料の納入状況その他の事情を考慮して定める基準に従い、所轄都道府県労働局長が定めるものとされている。(則44条)
- 事業主からの費用徴収の規定に係る徴収金は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう)または都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない。(則45条)
費用徴収の対象となるのは、療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して「3年以内」に支給事由が生じたもの(年金給付については、この期間に支給事由が生じ、かつ、この期間に支給すべき保険給付に限る)に限られる。(平成5年6月22日発労徴42号、基発404号)
- 費用徴収の対象期間が「3年以内」に限定されるのは、事実関係の明確化などが困難になること、事業主への責任追及の長期化は法律関係の早期安定を図るという趣旨に反することなどにあります。
| 徴収金の金額 | 対象となる保険給付 | |
|---|---|---|
| 事業主の「故意による保険関係届の未提出期間」中における保険給付 | 支払の都度、保険給付の額の100% |
「通勤災害」についても費用徴収されます。 |
| 事業主の「重過失による保険関係届の未提出期間」中における保険給付 | 支払の都度、保険給付の額の40% | |
| 「一般保険料滞納期間中」の保険給付 | 支払の都度、保険給付の額に滞納率(40%上限)を乗じて得た額 | |
| 事業主の故意または重過失により生じさせた業務災害 | 支払の都度、保険給付の額の30% |
事業主の故意または重大な過失により生じた「通勤災害」に関しては、費用徴収は行われません。 |
費用徴収の対象となるのは、療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して「3年以内」に支給事由が生じたもの(年金給付については、この期間に支給事由が生じ、かつ、この期間に支給すべき保険給付に限る)に限られる。(平成5年6月22日発労徴42号、基発404号)
- 費用徴収の対象となる保険給付は、休業(補償)等給付、傷病(補償)等年金、障害(補償)等給付、遺族(補償)等給付、葬祭料等(葬祭給付)である。(昭和47年9月30日基発643号、平成8年3月1日基発95号、平成13年3月30日基発233号、令和2年8月21日基発0821第1号)
- 言い方を変えると、以下は費用徴収の対象となりません
- 療養(補償)等給付 ⇨ 療養は治療そのものに関わるため
- 介護(補償)等給付 ⇨ 介護は労働基準法上の災害補償に規定がなく徴収の限度額を設定できないことや生命維持に影響を与えるため
- 二次健康診断等給付(及び特別支給金) ⇨ 二次健康診断等は労働基準法上の規定がなく疾病予防が目的のため
- 言い方を変えると、以下は費用徴収の対象となりません
- 費用徴収の対象となるのは、療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して「3年以内」に支給事由が生じたもの(年金給付については、この期間に支給事由が生じ、かつ、この期間に支給すべき保険給付に限る)に限られる。(平成5年6月22日発労徴42号、基発404号)
- 事業主が概算保険料のうち一般保険料を督促状の指定期間内に納付しない場合に事故が生じたときは、原則として費用徴収が行われるが、天災事変その他やむを得ない事由により保険料を納付することができなかったと認められる場合には費用徴収は行われない。(平成5年6月22日発労徴42号、基発404号)
- 費用徴収の対象となるのは、療養を開始した日(即死の場合は事故発生の日)の翌日から起算して「3年以内」に支給事由が生じたもの(年金給付については、この期間に支給事由が生じ、かつ、この期間に支給すべき保険給付に限る)に限られる。(平成5年6月22日発労徴42号、基発404号)
不正受給者からの費用徴収
偽りその他不正の手段により保険給付を受けた者があるときは、政府は、その保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。(法12条の3第1項)
- 労災保険法、国民年金法、厚生年金保険法などの「年金給付」があるものは、「不正の手段」と表現しますが、雇用保険法や健康保険法などの短期給付のものは、「不正の行為」と表現しています。
事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行なわれたものであるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者と連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。(法12条の3第2項)
「保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部」とは、保険給付を受けた者が受けた保険給付のうち、偽りその他不正の手段により給付を受けた部分(不当利得分に相当する価額)をいいます。(昭和40年7月31日基発906号)
- 不正受給者が受けた保険給付のうち、「不正手段に対応する部分」を費用徴収します。「保険給付に要した費用に相当する金額の全部」を費用徴収するのではありません。
偽りその他不正の手段によって保険給付を受けた場合であっても、罰則の適用はありません。(法51条~法54条)
不正受給に係る事業主・保険医療機関等への措置
① 不正受給に係る事業主等に対する措置
| 法令 | 内容 |
|---|---|
| 労災保険法 | 事業主が虚偽の報告又は証明をしたためその保険給付が行われたものがあるときは、政府は、その事業主に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。 |
| 雇用保険法 | 事業主等が偽りの届出、報告又は証明をしたためその失業等給付が支給されたものであるときは、政府は、その事業主等に対し、その失業等給付の支給を受けた者に連帯して失業等給付の返還又は納付金を納付することを命ずることができる。 |
| 健康保険法 | 事業主が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関等で診療に従事する保険医若しくは主治の医師が、保険者に対する報告を正当な理由なく拒み、その他保険給付の拒絶をしたものであるときは、保険者は、当該事業主等に対し、保険給付を受けた者に連帯して徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
|
| 国民年金法 | ― |
| 厚生年金保険法 | ― |
② 不正受給に係る保険医療機関等に対する措置
| 法令 | 内容 |
|---|---|
| 健康保険法 | 保険者は、保険医療機関等が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払等を受けたときは、その額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。 |
| 労災保険法 | ― |
| 雇用保険法 | ― |
| 国民年金法 | ― |
| 厚生年金保険法 | ― |
不正受給に係る「連帯納付命令」
- 労災保険法→事業主に対する連帯納付命令
- 雇用保険法→事業主、職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は指定教育訓練実施者に対する連帯納付命令
- 徴収法→労働保険事務組合に対する連帯納付命令
- 健康保険法→事業主、保険医又は主治の医師に対する連帯納付命令
- 国民健康保険法→保険医又は主治の医師に対する連帯納付命令
不正受給者からの費用徴収に係る徴収金を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときに、時効によって消滅する。(法12条の3第3項)
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索
サイドメニュー
- Between Japan and Nepal
- Tokutei Ginou
- QandA
- Shop info
- English