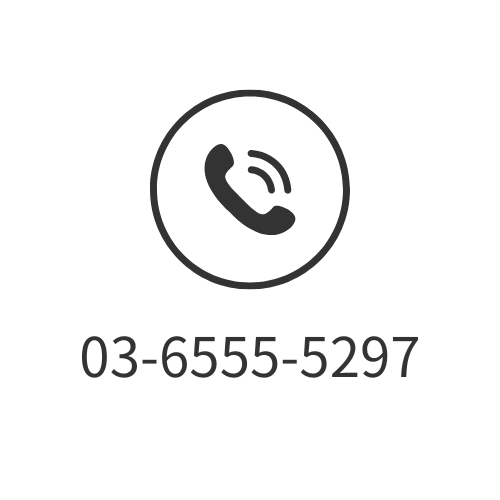品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
高年齢雇用継続基本給付金
高年齢雇用継続基本給付金は、60歳以降の再雇用などで賃金が低下した労働者の雇用継続を支援するための雇用保険の給付制度です。
この制度は、2025年(令和7年)4月1日に改正が行われ、給付率の引き下げなど、内容が変更されています。
- 高年齢雇用継続基本給付金は、「65歳に達した日の属する月」まで「月」単位で支給されます。
例えば65歳の誕生日が4月28日であるなら、4月分まで支給されることになります。被保険者は、月の途中で65歳以上となるため、「高年齢被保険者」にも高年齢雇用継続基本給付金が支給される余地がほんの少しだけ生じることになります。
目 次
高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、介護休業給付金
- 高年齢雇用継続基本給付金 本ページ
| 1 | 被保険者が60歳に達した日または60歳に達した日後において、算定基礎期間に相当する期間(被保険者であった期間)が、5年以上あること |
|---|---|
| 2 | 「支給対象月に支払われた賃金の額」が、みなし賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額を下っていること |
| 3 | 2026改正支給対象月に支払われた賃金の額が支給限度額(386,922円)未満であること。 |
| 4 | 2026改正支給対象月における高年齢雇用継続基本給付金の額として算定された額が3,014円の80%相当額(2,411円)を超えていること。 |
- 60歳到達日において被保険者であった期間が5年未満であっても、その後5年以上になった場合には、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができます。
- 支給限度額の自動変更による改定日は毎年「8月1日」ですので、8月以後の雇用月より当該変更後の支給限度額を基準として支給額を算定することとなります。
- 「被保険者であった期間」は基本手当における「被保険者であった期間」の取扱いと同様に、当該被保険者であった期間に係る被保険者資格を取得した日の直前の被保険者資格を喪失した日が当該被保険者資格の取得日前1年の期間内にある場合であって、この期間内に基本手当または特例一時金の支給を受けていない場合に通算される。
- 被保険者であった期間と被保険者であった期間との間が、1年以内で基本手当などの支給を受けていない場合には、「あわせて5年以上」となります。
- 高年齢雇用継続基本給付金を受給している途中でA社を離職し、基本手当などを受給しないまま、「1年を超えて」B社に再就職した場合、B社においては高年齢雇用継続基本給付金を受給することはできません。
これに対し、高年齢雇用継続基本給付金の受給資格者が、被保険者資格喪失後、基本手当の支給を受けずに、「1年以内」に雇用され被保険者資格を再取得したときは、新たに取得した被保険者資格についても引き続き高年齢雇用継続基本給付金の受給資格となり得ます。
(厚生労働省HP、Q&A~高年齢雇用継続給付~Q12)
支給対象月に支払われた賃金の額
高年齢雇用継続基本給付金に係る「支給対象月に支払われた賃金の額」とは、60歳に達した日の属する月以後に支払われる賃金の額をいうが、非行、疾病または負傷、事業所の休業またはこれらの理由に準ずる理由であって公共職業安定所長が定めるものにより支払を受けることができなかった賃金がある場合には、「その支払を受けたものとみなして」支給対象月における賃金の額が算定される。(法61条1項かっこ書、則101条の3)
- 「みなし賃金日額に30を乗じて得た額」の「75%相当額を下回っていること」が要件です。
- 退職をした場合「賃金日額」⇨退職をしていないので「みなし賃金日額」
- みなし賃金日額が30万円だった。支給対象月に支払われる賃金の額が18万円であるところ、疾病などが理由で6万円分の賃金の支払を受けることができませんでした。この場合の低下率の算定は?
この場合、現実に受け取った賃金額の12万円で低下率を算定するのではなく、疾病による額を実際に支払われた賃金額に加えた18万円で算定します。すなわち、18万円÷30万円=60%が低下率となります。
低下率の算定においては、あくまでも「年齢」が原因の低下部分がその算定の基礎となります。
- 月の「全部」について介護休業または育児休業を取得した場合には、支給対象月とは認められませんが、月の「一部」について休業を取得した場合には、支給対象月と認められ、高年齢雇用継続基本給付金が支給されます。
- 初日から末日までの間に引き続き介護休業給付金または育児休業給付金の支給対象となる休業を取得した場合、その月は高年齢雇用継続基本給付金を受けることはできません。
| 「支給対象月」に該当するか? | ||
|---|---|---|
| 月の初日から末日まで「まるまる被保険者」だった? | ||
| ↓ YES | ↓ NO | |
| 月の初日から末日まで「まるまる休業・休職」していた? (他の給付金を受け取っているか?) | ||
| ↓ NO | ↓ YES | |
| 「支給対象月」に該当 | 「支給対象月」に該当しない | |
支給申請手続(初回)
被保険者は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、支給対象月の初日から起算して4か月以内に、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に60歳到達時等賃金証明書等の書類を添えて、事業主を経由してその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由のため事業主を経由して当該申請書の提出を行うことが困難であるときは、事業主を経由しないで提出を行うことができる。(則101条の5第1項)
- 高年齢雇用継続給付の申請手続は、原則として、「事業主」を経由して行う必要があります(本人の希望があれば本人が行うこともできます)。
- 高年齢雇用継続給付の支給は、最大でおよそ5年になるため、複数回、支給申請を行います。
| 「60歳到達時等賃金証明書」 | |
|---|---|
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 原則として必要 |
| 高年齢再就職給付金 | 不要
|
- 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。(則101条の5第7項)
- 事業主を経由して申請書の提出を行う場合であって、当該事業主が特定法人の事業所の事業主である場合には、電子申請により行う(2回目以降の申請手続についても同様)。(則101条の5第8項・第10項)
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索
サイドメニュー
- Between Japan and Nepal
- Tokutei Ginou
- QandA
- Shop info
- English