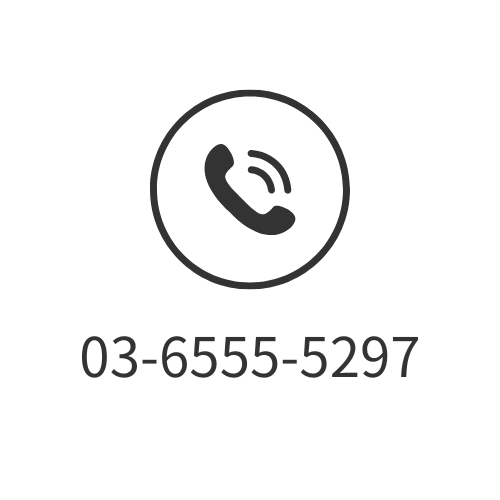品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
雇用保険法
被保険者
個人事業主及び法人の代表者
代表取締役は、雇用保険の被保険者とはならない。(行政手引20351)
- 「代表取締役」は、原則として、労災保険法及び雇用保険において適用除外の取扱いを受けますが、労災保険については、特別加入により加入する可能性があります。
「個人事業主」も、原則として、労災保険法及び雇用保険において適用除外の取扱いを受けますが、労災保険については、特別加入により加入する可能性があります。
参照 → 各法律における法人の役員など
2以上の雇用関係を有する者
同時に2以上の雇用関係を有することとなった者(いわゆる在籍出向など)については、その者が生計を維持するに必要な主たる賃金を受ける一の雇用関係、すなわち、主たる雇用関係についてのみ、その被保険者資格が認められる。(行政手引20352)
在籍出向の場合、出向者が、徴収法において出向元事業と出向先事業とのいずれの保険関係による「労働者」であるかについては、出向の目的、出向元事業主と出向先事業主との間で当該出向者の出向につき行った契約、出向先事業における出向者の労働の実態等に基づき、労働関係の所在を判断して、決定します。
(昭和35年11月2日基発932号)
- なお、労災保険においては、2以上の事業に使用される者は、それぞれの事業において適用労働者となります。
長期欠勤中の者
労働者が長期欠勤している場合であっても、雇用関係が存続する限り、「賃金の支払を受けていると否とを問わず」被保険者となる。(行政手引20352)
したがって、この長期欠勤期間は、基本手当の所定給付日数等を決定するための基礎となる算定基礎期間に「算入」されることになります。(行政手引20352)
- なお、欠勤期間中に賃金の支払がなければ、その間の雇用保険料はかかりません。こういったことから雇用保険法1条では、保険料の反対給付たる「保険給付」という表現をとらず「必要な給付」という表現を用いています。
国外で就労する者
- 日本国の領域外で就労する場合には、次のような取扱いとなる。(行政手引20352)
| 国外で就労する者の取扱い |
|---|
|
| 日本国に在住する外国人 | 原則として被保険者となる | 外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者を除き、国籍(無国籍を含む)のいかんを問わず被保険者となる。(行政手引20352) |
|---|---|---|
| ワーキング・ホリデー制度による入国者 | 被保険者とならない | 主として休暇を過ごすことを目的として入国し、その休暇の付随的な活動として旅行資金を補うための就労が認められるものであることから、被保険者とならない。(行政手引20352) |
技能実習生 | 原則として被保険者となる | 日本の民間企業等に技能実習生(在留資格「技能実習 1 号イ」、「技能実習 1 号ロ」、「技能実習 2 号イ」及び「技能実習 2 号ロ」の活動に従事する者)として受け入れられ、技能等の修得をする活動を行う場合には、受入先の事業主と雇用関係にあるので、原則として、被保険者となる。(行政手引20352) |
| 雇用保険の適用除外 |
|---|
| ① 所定労働時間が20時間未満である者 |
| ② 継続して31日以上雇用されることが見込まれない者(雇用保険は30日がベース。それを超えるということ) |
| ③ 季節的に雇用される一定の者(出稼ぎ労働者) |
| ④ 学生または生徒であって一定の者 |
| ⑤ 政令で定める漁船に乗り組む船員 (漁は季節的) |
| ⑥ 国、都道府県等に雇用される一定の者 |
参照 派遣労働者の取扱い
| 適用除外 | 適用除外とされない者(被保険者となる者) |
|---|---|
| 1週間の所定労働時間が20時間未満である ( 法定労働時間の1/2未満 )
|
|
| 同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
|
|
| 適用除外 | 適用除外とされない者 (被保険者となる者) | 短期雇用特例被保険者 (法38条1項、平成22年厚労告154号) |
|---|---|---|
| 季節的に雇用される者であって、次のいずれかに該当するもの
| ||
季節的に雇用される者であって、1週間の所定労働時間が20時間未満である者は、適用除外者①に該当 |
| 季節的に雇用される者であって
|
令和4年3月31日以降に就労していなかった者が、令和6年4月1日に65歳に達し、同年7月1日にX社に就職して1週当たり18時間勤務することとなった後、同年10月1日に季節的事業を営むY社に就職して1週当たり12時間勤務し二つの雇用関係を有するに至り、雇用保険法第37条の5第1項に基づく特例高年齢被保険者となることの申出をしていない場合、同年12月1日時点において当該者は雇用保険法の適用除外となる。
| 適用除外 | 適用除外とされない者 (被保険者となる者) | |
| 学校教育法の学校の学生または生徒であって、一定のもの
|
| |
| 政令で定める漁船(特定漁船以外の漁船)に乗り組む船員
|
| |
| 国などに雇用される者のうち、退職手当受給対象者 | 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則などに基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、厚生労働省令で定めるもの(法6条6号、則4条1項)
国などに雇用される者(則4条)
|
則4条
1項 法6条6号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
- 国又は独立行政法人通則法に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という)の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であって、職員とみなされないものを除く)
- 都道府県、地方自治法の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は地方独立行政法人法に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という)であって設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるものの事業に雇用される者であって、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
- 市町村又は地方自治法の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であって設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校教育法の学校、各種学校若しくは認定こども園法に規定する幼保連携型認定こども園における教育、研究若しくは調査の事業を行うものその他市町村に準ずるものの事業に雇用される者であって、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によって、その承認を受けたもの
| 常用型 | 「派遣元」で被保険者となる |
|---|---|
| 登録型 | 次のいずれにも該当する場合「派遣元」で被保険者となる |
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索
サイドメニュー
- Between Japan and Nepal
- Tokutei Ginou
- QandA
- Shop info
- English