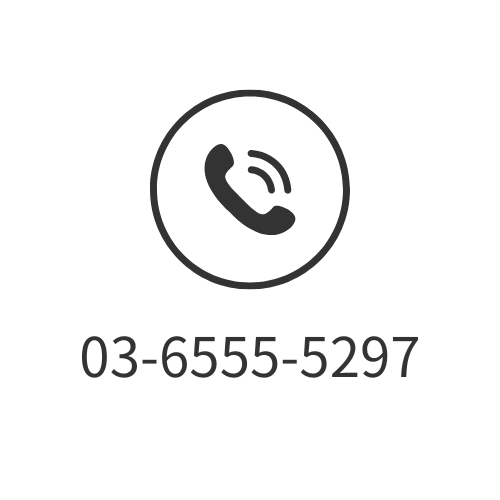品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
労働基準法の「労働者」
労働者の定義
「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。(法9条)
労働基準法では現実に「使用され」「賃金を支払われる」関係に立つ者を「労働者」としています。
これに対し、労働組合法では「労働者」を「賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者」としていて、「失業者」を含んでいます。
法人の代表など
労働基準法にいう労働者とは、事業または事務所に使用される者で賃金を支払われる者であるから、法人、団体、組合などの代表者または執行機関たる者のように、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は労働者ではない。(昭和23年1月9日基発14号、平成11年3月31日基発168号)
なお、取締役は会社との関係において、雇用契約ではなく、会社法330条に基づき民法643条の委任契約を締結します。この契約では、取締役が会社の意思決定や業務執行を委託され、その対価として報酬が支払われることが一般的です。
| 該当箇所 | 趣旨 | |
|---|---|---|
| 「職業」の種類 | 労働基準法で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。(法9条) | 肉体労働、精神労働など、その行われる労働の性質を言う |
| 「業務」の種類 | 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。(法22条1項) | 「経理」「総務」「営業」など |
| 「事業」の種類 | この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。 | 法別表第1の「製造業」「建設業」など |
| 「指揮監督下の労働」に関する判断基準 |
|
|---|---|
| 「報酬の労務対償性」に関する判断基準 | 報酬が時間給を基礎として計算されるなど労働の結果による較差が少ない、欠勤した場合には応分の報酬が控除され、いわゆる残業をした場合には通常の報酬とは別の手当が支給されるなど報酬の性格が使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることに対する対価と判断される場合には、使用従属性を補強することとなる。 |
| 法律 | 労働者の定義 | 失業者 |
|---|---|---|
| 労働基準法9条 | 職業の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 | 含まない |
| 労働契約法2条1項 | 使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。 | 含まない |
| 労働組合法3条 | 職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。 | 含む |
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索
サイドメニュー
- Between Japan and Nepal
- Tokutei Ginou
- QandA
- Shop info
- English