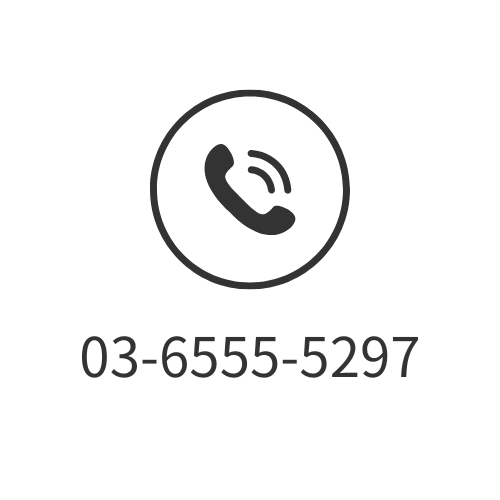品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
1.養子縁組
養子縁組とは、法律上の手続によって実際の血縁がない者同士に親子関係を新たに作ることです。そのため、法律上の手続が順調であれば、同国人だけでなく、外国人と養子縁組を結ぶこともの可能になります。この養子縁組が成立するかどうかについて判断するときには、それぞれ実質的成立要件と形式的成立要件があります。
2.養子縁組の成立要件
養子縁組が成立するかどうかについて判断(成立要件を満たしているかどうかを判断)する時には、まずその判断の基準となる法律(準拠法)を決めなければなりません。
実質的成立要件を満たしているかどうかを判断する際には、養親となる者の本国法が準拠法になります。養親の本国法で定める成立要件に加えて、養子の本国法が要求する保護要件も成立要件の判断基準になります。これらを満たすことによって、実質的成立要件を満たします。
※養子縁組の効力も、養親の本国法によります。
形式的成立要件を満たしているかどうかを判断する際には、養親となる者の本国法または行為地法が準拠法になります。
!日本の場合では、行為地法に従って、外国で外国の手続で養子縁組を行った場合には、日本人である養親は、3ヶ月以内に、縁組証書の謄本をその国に駐在している日本の大使、公使又は領事に提出しなければなりません。
3.実質的成立要件
通則法によれば、実質的成立要件は多くあり、代表的なものは下のようになります。
①養子縁組の許否
→日本では認められていますが、イスラム法などでは養子縁組がそもそも認められていません。
②養親及び養子の表意能力
③養親及び養子となるための年齢、年齢差
→日本の場合では、養親になるためには20歳以上であることが必要になります。
④婚外子・尊属・年長者及び被後見人等を養子とすることの可否
→婚外子については言及されいませんが、尊属及び年長者は養子としてはならないと民法793条で定められています。
被後見人については、家庭裁判所の許可があれば、養子とすることは可能になります。
⑤法定代理人の代諾による縁組の可否
→日本法においては、15歳未満の者を養子にするためには、法定代理人の代諾が必要になるため、法定代理人の代諾による縁組を認めています。
⑥配偶者ある者の縁組の可否
→日本法では、配偶者ある者が縁組する場合にはその配偶者の同意を得ることが必要とされています。
⑦養子となる者の保護要件
→通則法によって、養子となる者の本国法において「その者若しくは第三者の承諾もしくは同意又は公的機関の許可その他の処分」を養子縁組の成立要件にしている場合、その要件(保護要件)をも備えなければならないと定められています。これは社会経験や判断能力が乏しい未成年者の保護のために設置されたものであり、未成年者保護の見地から合目的的であると判断されています。
→日本法上でも、養子が15歳以上の場合にはその承諾、15歳未満の場合には法定代理人の代諾、未成年養子の場合の家庭裁判所の許可など、様々定められています。
4.形式的成立要件
形式的成立要件は主に手続上のことになります。
①養子縁組届出
→日本で手続をする場合には、何人であるかにかかわらず、日本法に従って手続を行うことになります。
日本法においては、養親となる者と養子となる者とが、2名以上の証人が署名した書面で養親の本籍地又は所在地の市区町村へ養子縁組届を提出し、それが受理されることによって、養子縁組の効力が生じます。
→外国で手続をする場合には、日本人間の養子縁組である場合は、日本の大使などに対して届出をすることができます。養親が日本人である場合は、養親の本籍地の市区町村長への直接郵送になります。養親が外国人である場合は、養親の国籍国の法律に従って手続を進めていきます。
②必要書類
→日本の場合では、養親となる者の戸籍謄本、養子となる者の出生証明書・国籍証明書などが必要になります。未成年者である場合には家庭裁判所の審判書の謄本、同意を要する場合には同意書など、個人の事情によって異なる書類が必要になります。
実際に、成立要件を満たして、日本において養子縁組することができた場合の在留資格についてこちらをご覧ください。
(参考)出入国在留管理庁 ホームページ
入管関係法大全 2在留資格 出入国管理法令研究会/編著
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索
サイドメニュー
- Between Japan and Nepal
- Tokutei Ginou
- QandA
- Shop info
- English