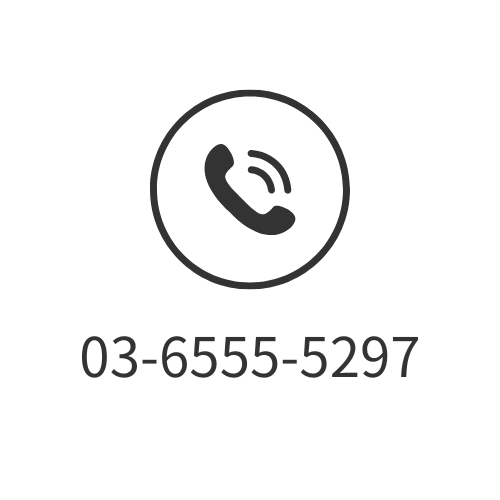品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
1.養子縁組
養子縁組とは、法律上の手続によって実際の血縁がない者同士に親子関係を新たに作ることです。そのため、法律上の手続が順調であれば、同国人だけでなく、外国人と養子縁組を結ぶこともの可能になります。実際に日本で養子縁組が成立した場合、その養子の在留資格には、どのような影響を及ぼすのでしょうか?
2.養子に適用可能な在留資格
養子縁組が成立した後、養子に適用される在留資格として考えられるものは、以下の3つになります。
①日本人の配偶者等
②定住者
③家族滞在
3.日本人の配偶者等
「日本人の配偶者等」は日本在留中に行う活動の範囲についての制限はありません。また、この在留資格を持つ人も必ず日本人の扶養を受けることを要しません。しかし、この在留資格が養子に適用されるためには、養親が日本人であり養子は普通の養子であるだけではなく、特別養子であることが必要になります。
特別養子とは、養子縁組によって実の親子と同様な親子関係を成立させることです。
①15歳未満の子の利益のために特に必要である
②家庭裁判所の審判によって成立する
特別養子縁組が成立すると、原則として、その特別養子は実親との親子関係は消滅し、戸籍上養親夫婦の嫡出子となります。そのため、「日本人の配偶者等」が適用されます。普通の養子は血縁上も戸籍上も日本人の子にならないため、「日本人の配偶者等」は適用されません。ただし、例外としては、その普通養子の本国法において、養子制度が日本の特別養子制度と同様な効果がある場合には、戸籍上に「特別養子」として記載し、「日本人の配偶者等」が適用されます。
4.定住者
「定住者」とは、特別な理由を考慮して居住を認めるのが相当である外国人を受け入れるために設けられた制度です。この在留資格についても、日本在留中に行う活動の範囲についての制限はありません。
養子に適用する場合には「定住者告示7号」があります。「定住者告示7号」では、日本人、永住者、特別永住者又は一年以上の在留期間を指定されている定住者の扶養を受けている6歳未満の養子を対象にしています。そのため、申請時において、6歳を超える養子に「定住者告示7号」は適用されません。
※「定住者告示7号」を持って「定住者」の在留資格を取得した後に、6歳を超えた場合は、退去強制事由が発生せず、特段の素行不良状態とならない限りは、更新許可が認められる可能性が高いです。
また、6歳を超えても、真摯な意思による養子縁組をし、今後長期間日本で養親と一緒に生活する意思がある場合にも認めることが多いです。従来では、6歳以上であるが、本国において当該子を養育監護する者がいない場合などにも「定住者」と認められることは多くあります。
5.家族滞在
「家族滞在」とは、一定の在留資格を持って日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるための制度です。これは、上の2つとは違って、資格外活動許可を得なければ、就労活動などが制限されてしまいます。
この在留資格が養子に適用されるためには、その養親に扶養する意思が求められ、さらに扶養することが可能であると証明できる経済的裏付けが求められています。この点から、養子は20歳以上であっても、学生の身分であったり、親の扶養を受けている者に該当すれば、「家族滞在」は適用されます。
!「家族滞在」は外国人の家族を受け入れるための制度であるため、養親が日本人である場合は当然ながら適用されません。
6.まとめ
養子となっても、在留資格に影響を及ぼすものはすごく限られています。
「日本人の配偶者等」→特別養子のみ
「定住者」→特別養子、6歳未満の養子、6歳以上の扶養を受けている養子は○
→6歳以上の養子は扶養を受けていない場合は、理論上は可能ですが、厳しい審査になります。
「家族滞在」→養親が外国人かつその扶養を受けている養子のみ
(参考)出入国在留管理庁 ホームページ
入管関係法大全 2在留資格 出入国管理法令研究会/編著
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索
サイドメニュー
- Between Japan and Nepal
- Tokutei Ginou
- QandA
- Shop info
- English