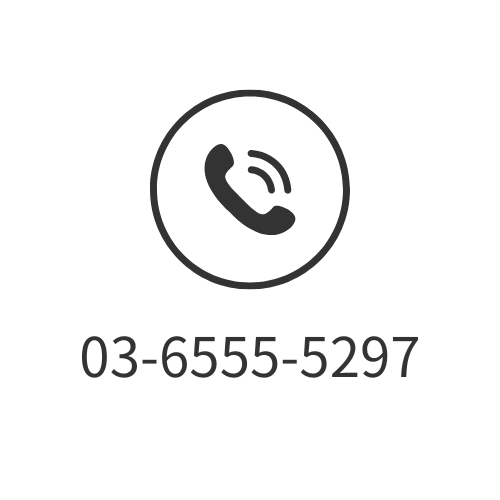品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
外国会社の活動に必要な手続
会社の設立に関する基礎知識
-1 総論
-2 定款と登記
.1 定款
.2 定款認証の特別処理
.3 テレビ電話による電子定款の認証
.4 外国会社の活動に必要な手続 本ページ
.5 外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続
.6 電子定款の認証と設立登記のオンライン同時申請制度
-3 事業計画書
-4 外国人と銀行口座
-5 外為法上の対内直接投資(対日直接投資)に係る事前届出及び事後報告の義務
-6 その他類型別情報
.1 外国企業の日本支店を設立する場合
.2 一般社団法人
外国会社とは
1 定義
「外国会社」とは、「外国の法令に準拠して設立された法人その他の 外国の団体であって、会社と同種のもの又は会社に類似するもの」をいいます(会社2 ②)。
「法人その他の外国の団体」とされているため、設立準拠法によって法人格が与えられていなくとも、会社法上の「会社」(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社 (会社2①))と同種のもの又は「会社」に類似するものであれば、「外国会社」となり ます。
2 日本における代表者の選任・登記
外国会社が日本において取引を継続してしようとするときは、日本における代表者を定めなければなりません(会社817Ⅰ前段)。そして、外国会社が初めて日本における代表者を定めたときは、3週間以内に外国会社の登記をしなければならず(会社933 Ⅰ)、たとえ日本における代表者を定めた場合でも、外国会社の登記をするまでは、日 本において取引を継続してすることができません(会社818Ⅰ)。これに違反して取引をした者は、その相手方に対して、外国会社と連帯して当該取引によって生じた債務を 弁済する責任を負います(会社818Ⅱ)。
したがって、外国会社が日本で事業を行おうとするときは、
という2つの手続を踏む必要があります。
日本における代表者の選任と営業所の設置
1 日本における代表者
日本における代表者は、外国会社の日本における業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を持ちます(会社817Ⅱ)。会社法においては、日本における代表者の選任方法・代表者の資格に関する規定は存在せず、外国会社の本国の代 表者や役職員などの一定の地位にある者である必要はありません。もちろん、本国 の代表者が日本における代表者を兼任することも可能です。契約により日本の弁護 士等を選任することも可能です。
また、個人だけでなく、法人が外国会社の日本における代表者になることも可能です。法人が日本における代表者になる場合、当該法人の代表者等が日本における 代表者の職務を行うべき者として外国会社の登記を申請することになります(令4・ 6・24民商307)。
日本における代表者のうち1人以上は、日本に住所を有する者でなければ なりません(会社817Ⅰ後段)。株式会社等の内国会社の代表者については、国内居住要件は 廃止されましたが、外国会社の日本における代表者については、国内居住要件が維 持されていますので、注意が必要です。 弁護士等を日本における代表者に選任した場合、当該弁護士の事務所の所在場所等も登記すべき日本における代表者の住所に該当することとされています。 法人が日本における代表者となる場合、当該法人は、日本に本店を有する内国会社、日本において登記された外国会社等でなければなりません(令4・6・24民商307)。
2 営業所の設置
外国会社が任意に営業所を設置した場合、当該営業所の所在場所は登記事項となります(会社933Ⅲ)。
外国会社の登記
1 登記の申請
外国会社が初めて日本における代表者を定めたときは、3週間以内に外国会社の登記をしなければなりません。登記を申請する登記所は、次の基準によって決定されます(会社933Ⅰ)。
⑴ 日本に営業所を設けていない場合
日本における代表者(日本に住所を有するものに限ります。)の住所地を管轄する登記所となります。
⑵ 日本に営業所を設けた場合
当該営業所の所在地を管轄する登記所となります。
2 登記事項
外国会社の登記においては、日本における同種の会社又は最も類似する会社の登記事項(株式会社について会社911Ⅲ、合名会社について会社912、合資会社について会社913、合同会社について会社914)に加えて、次に掲げる事項を登記しなければなりません(会社933Ⅱ・ Ⅲ、会社規220Ⅰ⑥)。
① 外国会社の設立の準拠法
② 日本における代表者の氏名及び住所
③ 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、準拠法 の規定による公告方法
④ 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときで、貸借対 照表に相当するものの内容を電磁的方法により開示するときは、ウェブページアド レス
⑤ 日本における公告方法に関する事項
3 登記事項ごとの留意点
外国会社の登記における登記事項は、外国会社特有の登記事項に加え、日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従うことになります(会社933Ⅱ・Ⅲ)。
⑴ 商号
外国会社の本国の商号を登記しますが、外国会社は、当然商号も本国の文字をもっ て表示されているため、これをどのような表記で登記すべきかが問題となります。
ア ローマ字その他の符号
該当するローマ字その他の符号を用いた商号であれば、本国の表記をそのまま登記することが可能です(商登規50、商業登記規則第51条の2第1項の規定により 法務大臣が指定する商号の登記に用いることができる符号に関する件(平14・7・31法務告315))。 商号の登記に使用できるローマ字その他の符号は次のとおりです。
① ローマ字(大文字及び小文字)
② アラビヤ数字
③ 「&」(アンパサンド) 「’」(アポストロフィー) 「,」(コンマ) 「-」(ハイフン) 「.」(ピリオド) 「・」(中点)
③の符号を使用できるのは、字句(日本文字を含みます。)を区切る場合に限られ、 商号の先頭又は末尾に使用することはできません。ただし、「.」(ピリオド)について は、その直前にローマ字を用いた場合に省略を表すものとして商号の末尾に使用する ことができます。なお、空白(スペース)は、ローマ字を用いた複数の単語の間を区切る場合のみ使用することができます(平14・7・31民商1841)。
イ 漢字
中国や韓国などの漢字使用国の商号については、商号として用いられている漢字が 日本で正字として通用しているのであれば、そのまま登記することも可能です。商号 として用いられている漢字が正字でない場合は、その漢字に相応する正字に引き直し て登記することになります。
ウ その他の文字
その他、キリル文字、ギリシア文字等については、商号として登記することができ ないため、カタカナに引き直して表示して登記するほかありません。
エ 会社の種類の表記
なお、外国会社の商号については、会社の種類を表す「株式会社」「合同会社」「合 名会社」「合資会社」等の文字を使用する必要はなく、会社の種類を表す部分について も商号のほかの部分と同様に、カタカナ、ローマ字、漢字等を用いて表示します(平5・11・5民四6928、登記研究360号96頁)。例えば 「Inc.」「有限公司」等と表示します。
⑵ 本店
外国会社の本国の本店所在場所を登記しますが、商号とは異なり、ローマ字であってもそれが符号として用いられている場合(XYZビルA館、何丁目何番B‐●号等)を除き、本店の登記で使用することはできません(昭43・1・26民事甲1参照)。
したがって、本店の登記は、原則として外国語の発音をカタカナに引き直して表記 して登記しますが、漢字使用国については、商号と同様に正字である漢字については、 漢字表記のまま、そうでない漢字については正字に引き直して、漢字表記で登記することが可能です。また、「国」「州」「市」等の行政区画を表す語を訳として表示して登 記しても差し支えありません。
なお、英米法国においては、「登録事務所」(Registered Office)と「営業の中心的な 場所」(Principal Office)の2つの概念が存在しますが、「本店」としては「登録事務所」を登記すべきとされています。
⑶ 会社設立の年月日
外国会社の本国の会社設立年月日を登記します。西暦で登記をすることも可能で す。
⑷ 目的
具体性を欠いた目的を登記した外国 会社が、金融機関において「いかなる事業を行っているのか不明である」との理由で 口座開設を拒否されるような不利益を避けるた め、実務的には外国会社が現に行っている又は将来行おうとしている事業を業務方法 書などから読み取り、具体的に登記することが適当です。
⑸ 役員に関する事項
役員に関する事項としては、「資格」「住所」及び「氏名」が登記事項となります。
ア 住所・氏名
「住所」及び「氏名」は、発音をカタカナで表記して登記することが原則ですが、 漢字使用国については、漢字(正字のみ)表記で登記をすることが可能です。 住所については、符号として用いられている場合を除き、ローマ字で登記すること ができないこと、住所に「国」「州」「市」等の行政区画を表す語を表示することがで きることは本店の登記と同様です。 氏名については、登記上「スペース」を用いることができないため、「スペース」の 代わりに「・」(中点)を用いることが通常です。例えば「●●●● ●●●」につい ては「●●●●・●●●」と登記するのが一般です。
イ 資格
役員の「資格」(肩書)については、例えば「Chief Executive Officer」、「Chief Financial Officer」は、それぞれ 「チーフ・エグゼクティブ・オフィサー」、「チーフ・ファイナンシャル・オフィサー」のように本国の会社の肩書の 発音をカタカナに引き直して(漢字使用国の場合は漢字表記のまま)登記するのが妥当です。
4 提出書類
⑴ 登記添付書類
外国会社が初めて日本における代表者を定めたときの外国会社の登記の申請書に添付すべき書類は次のとおりです(会社933Ⅰ、商登129Ⅰ)。なお、代理人により登記を申 請する場合には、代理人の権限を証する書面(委任状)も併せて添付します(商登18)。
① 本店の存在を認めるに足りる書面
② 日本における代表者の資格を証する書面
③ 外国会社の定款その他外国会社の性質を識別するに足りる書面
④ 公告方法についての定めがあるときは、これを証する書面
各書類の具体例としては、①につき定款・設立証明書・本国官庁の証明書等、②につき外国会社の取締役会議事録・任命書・契約書等、③につき定款・設立証明書・業 務方法書・Annual Report(アニュアルレポート)等、④につき定款等がこれに該当す るとされています。
これらの書類は、いずれも外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲(以下「領事等」といいます。)の認証を受けたものでなければなりま せん(商登129Ⅱ)。「本国の管轄官庁」の具体例としては本国における公証人などがこ れに該当し、「日本における領事」とは、本国の在日領事館の領事を指します。
なお、外国語により記載されている文書を法務局に提出する際は、日本語訳の添付 が必要であるとされていますので、これらの書類についてはすべて日本語訳を添付する必要があります。翻訳者の資格に制限はありません。
⑵ 宣誓供述書の作成
外国会社の登記の添付書類は上記⑴のとおりですが、外国会社の定款や設立証明書 などには、必ずしもすべての登記事項が網羅されているとは限りません。また、それ らの書類には登記とは無関係な事項も多く含まれていることが通常です。登記事項が 網羅された書類をすべて収集しようとした場合、時に膨大な量となり、それらすべて に認証を受けたり、翻訳することは大きな負担となります。
そこで、実務上は登記事項を列挙した「宣誓供述書」を作成し、この宣誓供述書について領事等の認証を受けることで、上記⑴①ないし④の書類に代えることができる ことが認められています。実際の登記申請においては、宣誓供述書が用いられるケー スが大多数であると考えられます。
宣誓供述書は、あくまで供述者本人が宣誓供述書の内容が真実であることを宣誓した上、認証者の面前で署名したことのみを証明するものに過ぎず、これを認証した領事等が宣誓供述書の記載内容が真実であることを証明するものではありません。よって、少なくとも、宣誓供述書の作成に当たっては、その内容の真実性を確保するため、当該外国会社の定款、設立証明書、アニュアルレポート、取締役会議事録、 任命書等の客観的な資料を入手し、これを確認しながら作成すべきと考えます。
なお、宣誓供述は、外国会社の本国の代表者又は日本における代表者が行うことが原則です。
⑶ 印鑑の届出
オンラインによる登記の申請において印鑑の照合以外の方法により申 請人の申請権限を確認することができる一定の場合には、印鑑の提出を要しません。
ただし、書面により登記の申請をする場合には、登記の申請書に押印すべ き者、すなわち外国会社の日本における代表者が、印鑑を登記所に提出することにな ります(商登規35の2)。
印鑑の提出は、印鑑届書を提出する方法によって行います。印鑑届書には、必要事 項を記入の上、提出者が押印し、その印鑑につき、市町村長(特別区の区長を含むも のとし、地方自治法252条の19第1項の指定都市にあっては、市長又は区長若しくは総 合区長とします。)作成の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)を添付しなければ なりません(商登規9Ⅰ⑤・Ⅴ①)。
なお、印鑑届出者は日本に住所を有している必要はありませんので、日本在住と外国在住の2名の日本における代表者がいる場合、外国在住の日本における代表者のみ が印鑑を届け出ることも可能です。この場合、市区町村長作成の印鑑証明書を添付す ることはできませんので、これに代えて領事等の認証を受けた「署名証明書」を添付 しなければなりません。
登録支援/有料職業紹介のご相談はこちら
芸術家×起業家
お 一般社団法人芸商橋
BusinessArtBridge
サイト内検索
サイドメニュー
- Between Japan and Nepal
- Tokutei Ginou
- QandA
- Shop info
- English