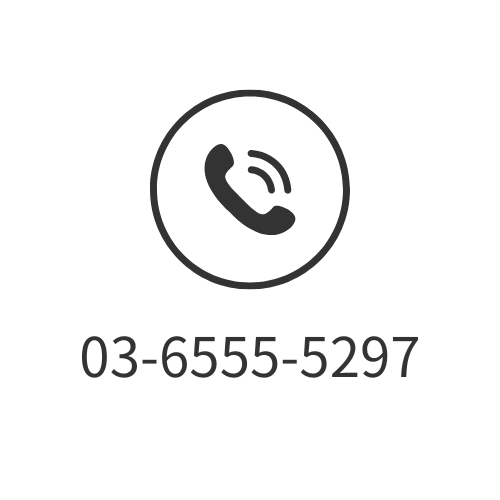品川駅直結。ビザ申請のご相談なら。
ソリューション行政書士法人
〒108-0075 東京都港区港南2-16-2 太陽生命品川ビル28F
在留資格「経営・管理」とは
日本において事業の経営を行い又は事業の管理に従事する活動するための在留資格のことです。(別表1の2)
| 要件 | 現行 | 旧制度 | ||
|---|---|---|---|---|
| ① | 資本金・出資総額 | 「3.000万円以上の資本規模」 | 「500万円以上の資本規模」 | |
| ② | 経歴・学歴(経営者) |
または
| 「経営・管理経験」には、在留資格「特定活動」に基づく起業準備活動を含む。 | 特になし |
| ③ | 雇用義務 | 「1人以上の常勤職員を雇用」 | 「常勤職員」の対象は、
| なし (資本金の代替要件として2人以上の雇用要件) |
| ④ | 日本語能力 | 申請者か常勤職員のいずれか1人に、「相当程度の日本語能力」を求める。 |
| 特になし |
| ⑤ | 新規事業計画の確認 | 原則として、公認会計士や中小企業診断士などによる新規事業計画の確認を義務づける | 特になし | |
既に在留中の者には施行後3年を経過した後の最初の在留期間更新許可申請時以降は、原則として改正後の上陸許可基準への適合を求めます。
なお、審査においては、経営に関する専門家の評価を受けた文書を提出いただくことがあります。
弊法人は多言語(英語・中国語)対応の公認会計士と提携していますので、お気軽にご相談ください。
本ページの目次
|
| |||
|---|---|---|---|
| 申請人が次のいずれにも該当していること | 改正内容 | ||
| 1 | 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。 ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。 | 自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。 | |
| 2 | 申請に係る事業の規模が次のいずれにも該当していること | ||
| イ | その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する常勤の職員(法別表第1の上欄の在留資格をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。 | 申請者が営む会社等において、1人以上の常勤の職員を雇用することが必要になります。 「常勤職員」の対象は、日本人、特別永住者及び「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」 、「定住者」に限ります。法別表第一の在留資格をもって在留する外国人は対象となりません。(在留資格「技術・人文知識・国際業務」ではこの要件をみたしません) | |
| ロ | 資本金の額又は出資の総額が3,000万円以上であること。 | <事業主体が法人である場合> <事業主体が個人である場合> | |
| 3 | 申請に係る事業の経営を行い、又は当該事業に従事する者(非常勤の者を除く。)のうちいずれかの者が、高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を有している者であって、かつ、申請人が当該事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する時において、本邦に居住することとしているものであること。 ⇨ くわしくはコチラ | 申請者又は常勤職員(注1)のいずれかが相当程度の日本語能力(注2)を有すること (注1)ここで言う「常勤職員」の対象には、法別表第一の在留資格をもって在留する外国人も含まれます。 (注2)相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力であり、日本人又は特別永住者の方以外については、以下のいずれかに該当することを確認します。
⇨ くわしくはコチラ | |
| 4 | 次のいずれかに該当していること。 | ||
| イ | 経営管理に関する分野又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野において博士の学位、修士の 学位又は専門職学位(学位規則第5条の2に規定する専門職学位をいい、外国に おいて授与されたこれに相当する学位 を含む。)を有していること。 | ||
| ロ | 事業の経営又は管理について3年以上の経験(注)を有 していること。 (注)特定活動の在留資格(法第 7条第1項第2号の告示で定める活動 のうち本邦において貿易その他の事業の経営を開始するために必要な事業所 の確保その他の準備行為を行う活動を 含む活動を指定されたものに限る。) をもって本邦に在留していた期間があ る場合には、当該期間を含む。 |
| |
| 5 | 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること | ||
|
| |||
| 1 | イ | 経営に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し | 在留資格決定時において提出する事業計画書について、その計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかを評価するものとして、経営に関する専門的な知識を有する者(注)の確認を義務付けます (注)施行日時点においては、以下の者が当該者に該当します。
なお、弁護士及び行政書士以外の方が、官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがありますので御留意願います。 |
| 1 | 事業内容について | 業務委託を行うなどして経営者としての活動実態が十分に認められない場合は、在留資格「経営・管理」に該当する活動を行うとは認められないものとして取り扱います。 |
|---|---|---|
| 2 | 事業所について | 改正後の規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。 |
| 3 | 永住許可申請等について | 改正後の許可基準に適合していない場合は、「経営・管理」、「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」(「経営・管理」活動を前提とするもの)からの永住許可及び「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可は認められません。 |
| 4 | 在留中の出国について | 在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、本邦における活動実態がないものとして在留期間更新許可は認められません。 |
| 5 | 公租公課の履行について | 在留期間更新時には、以下の公租公課の支払義務の履行状況を確認します 。 |
| ||
| 6 | 事業を営むために必要な許認可の取得について | 申請者が営む事業に係る必要な許認可の取得状況等を証する資料の提出を求めます。
|
|
| 外国人起業活動促進事業 スタートアップビザ | ||
|---|---|---|---|
| 在留資格 | 経営・管理 | 経営・管理 | 特定活動44号 |
| 在留期間 | 4月 | 1年・3年・5年 | 1年(更新1回・最長2年) |
| 会社設立 | 不要 ・定款認証は不要だが定款作成は必要 ・期間更新申請までに設立をする必要がある | 必要 | 不要 ・定款作成は不要 ・在留資格変更申請までに会社を設立をする必要がある |
| 事務所の確保
| 不要 ・期間更新申請までに事務所を確保する必要がある | 必要 | 不要 |
| 申請人の住居 | 不要 | 不要 | 6か月間の住居を明らかにする書類の提出が必要 ・賃貸契約書のコピー、または賃貸契約申込書など |
| 申請人の要件 | 特になし | 特になし | 外国人起業促進実施団体が要件を定める |
事業とは
1.適正性
日本において適法に行われるものであればよく、制限はありません。(風俗営業店でも可能です)
山脇康嗣. 〔新版〕詳説 入管法の実務-入管法令・内部審査基準・実務運用・裁判例- (Kindle の位置No.7002). 新日本法規出版株式会社
労働者を雇用する場合には労働保険、社会保険に加入することが必要であり、許認可を必要とする事業においては許認可を得る(見込みがある)ことが必要です。
2.安定性・継続性
新たに事業を始める場合には、事業計画 (収支見積等を含む) に具体性、合理性がなくてはならず、実現可能なものでなければなりません。
新日本法規出版『事例式 民事渉外の実務-手続・書式-』 ( 256ノ18ノ48 ) に
「他人に賃貸するために不動産を取得する行為」は、業として行う宅地や建物の売買となるため、それ自体が宅地建物取引法上の「宅地建物取引業の免許」が 必要な行為となります(宅地建物取引業法3)。
とありますが、以下の理由により疑問があります。
ポイントの整理
宅建業法に基づく「宅地建物取引業」とは、次の行為を業として行うことを指します(法第2条第2項)。
- 宅地または建物の売買
- 宅地または建物の交換
- 宅地または建物の貸借の代理または媒介
- 自己所有不動産の取得(購入)自体は、宅建業法の規制対象ではありません。
宅建業法が規制対象とするのは、不動産の売買・交換・貸借の代理や媒介を業として行う行為です - 他人に賃貸する目的であっても、自ら不動産を購入する行為は「自己取引」であり、宅建業免許は不要です。
- 不動産会社が土地や建物を仕入れて転売する場合(不動産転売業)などが『業として行う』『宅地または建物の売買』にあたります。
結論として、「他人に賃貸するために不動産を取得する行為」が宅建業免許を必要とする行為である、という記述は疑問があります。
そうでないと、一般の投資家が賃貸目的で不動産を購入する行為も宅建業免許が必要となる、ということになってしまいます。
経営を行うとは
事業の経営に実質的に参画することが必要です。通常、経営者、社長、取締役などがこれにあたりますが、名目上のものではいけません。申請人自身が事業に投資をすることは、要件ではありませんが、重要な判断要素となります。
上陸許可基準
事業所が日本国内に存在するか、確保されていること
規模等に応じた経営活動を行うための事業所を確保する必要があることから、自宅を事業所と兼ねることは、原則として認められません。
総務省が定める日本標準産業分類一般原則2項において、事業所について定義されています。
- 経済活動が単一の経営主体の下において一区画を占めて行われ ていること。
- 財又はサービスの生産と供給が,人及び設備を有して,継続的に行われていること。
たとえば、いわゆるバーチャルオフィスは「事業所」に該当しません。シェアオフィスは可能です。
申請時に、事業所の外観(事業所名が写っているもの)、内観(OA機器があるか、事務所を共有している場合に、明確に仕切られているか)を写真で添付することが一般的です。
在留資格の審査は通常、提出された書類を基に行いますが、内容に疑義が生じた場合には入管職員が現地調査を行います。今後、入管は審査時の実態調査を強化する方針です。
以下の(1)・(2)両方を満たす部分の金額について、上記ロの500万円に計上することが可能です。
(1)新株予約権の発行によって払い込まれた、返済義務のない払込金であること
(2)上記(1)の払込金について、将来
① 新株予約権が権利行使されることで払込資本となる場合
② 権利行使されずに失効し利益となる場合
のいずれであっても、資本金として計上することとしていること
なお、上記に係る提出資料としては、以下の書類等が必要となります。
ⅰ 新株予約権の発行にあたり締結された投資契約書(J-KISS型新株予約権契約書など)
ⅱ 上記ⅰの締結によって実際に払い込まれた額を証明する資料(通帳の写し若しくは取引明細書の写し)
ⅲ 上記ⅰの締結によって実際に払い込まれた額のうち、3000万円として計上して申請しようとする額について、将来、新株予約権が権利行使された際に資本金として計上することの誓約書等
新株予約権とは株式会社に対して行使することにより当該株式会社の株式の交付を受けることができる権利をいう。(会社法2条21号) この権利を保有していれば、決められた期間内は、決められた金額を払うことによって株式を取得することができ、会社の価値が増大すれば時価より低廉な金額で株式を取得できることになる。ストックオプションとして役員や従業員へのインセンティブ報酬とすることの機能のほかに、敵対的買収へのポイズンピルとしての機能などもある。
会社に対しての払込みは、2段階でなされる。
A 新株予約権の発行の際の払込がなされ(238条1項3号)、
B 新株予約権の行使の際に払込がなされる(236条1項2号3号)。
Bは、出資そのものであり、2分の1を超えない額は資本金に組み入れないことができ(445条2項)、Aに関しては、資本金の額とすることも、しないこともできる (前田330ページ)。
今回に関してはAの払込みを問題としている。
たとえば資本金200万円の会社に新株予約権の発行(A)として300万円を振り込んだ場合、その時点で300万円を資本金として計上していなくても、将来的に ①Bの払込額のうち300万円が資本金として計上されるか ②新株予約権が権利失効した際にはAの300万円が資本金として計上されるとされている場合には、
「500万円として計上する」
となっていると解します。
なお、Aも資本金と同じく純資産に分類されます。
| 1 | 法別表1の上欄の在留資格をもって在留する者は「常勤職員」に含まれない | 在留資格「技術・人文知識・国際業務」等は含まれない |
|---|---|---|
| 2 | 勤務が、休日を除き、毎日所定時間、常時その職務に従事していること | 週5日以上、かつ年間217日以上、かつ週30時間以上 |
| 3 | 職務に応じた給与が設定されている | |
| 4 | 使用者との契約が「直接雇用」「移籍出向(転籍)」であること | 「派遣」「請負」「在籍出向」ではNG |
在留資格「経営・管理」で必要とされる
日本語能力について
| 申請者(経営者)又は常勤職員のうちいずれかの者が、高度に自立して日本語を理解し、使用することができる水準以上の能力を有している者あること | 日本語能力を保有する「常勤職員」の対象には、在留資格「技術・人文知識・国際業務」「特定技能」も含まれます。 具体的には以下のパターンで要件をみたします。
相当程度の日本語能力とは、以下のいずれかに該当することを確認します
|
複数の者が事業の経営又は管理に従事している場合
許可事例の資本金額は旧制度での資本金額です。
それだけの人数の者が事業の経営又は管理に従事することが必要とされる 程度の事業規模、業務量、売上げ、従業員数等がなければならず、これらから見て、 申請人が事業の経営又は管理に主たる活動として従事すると認められるかどうかを判 断します。具体的には、
① 事業の規模や業務量等の状況を勘案して、それぞれの外国人 が事業の経営又は管理を主たる活動として行うことについて合理的な理由が認められ ること、
② 事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事す ることとなる業務の内容が明確になっていること、
③ それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬の支払いを受けることとなっていること
等の条件が満たされている場合には、それぞれの外国人について「経営・管理」の在留資格 に該当します。
(審査要領より)
許可事例
事例1
外国人A及びBがそれぞれ500万円出資して、本邦において輸入雑貨業を営む資 本金1000万円のⅩ社を設立したところ、Aは、通関手続をはじめ輸出入業務等海外 取引の専門家であり、Bは、輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家であ る。Aは、海外取引業務の面から、Bは、輸入品の管理及び経理面から、それぞれ にⅩ社の業務状況を判断し、経営方針については、共同経営者として合議で決定す ることとしている。A及びBの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割 合で支払われることとなっている。
事例2
外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を出資して、本邦において運送 サービス業を営む資本金1400万円のY社を共同で設立したところ、運送サービスを 実施する担当地域を設定した上で、C及びDがそれぞれの地域を担当し、それぞれ が自らの担当する地域について、事業の運営を行っている。Y社全体としての経営 方針は、C及びDが合議で決定することとし、C及びDの報酬は、事業収益からそ れぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。
事例3
外国人E及およびFは、それぞれ800万円及び200万円を出資して、本邦においてデジタルマーケティングに係る専門的トレーニングや教育を提供する事業を営む資本金1,000万円のZ社を設立するため、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業を活用して起業活動を行うこととしている。Eは、過去の起業や人材育成の経験を活かしCEO兼ヘッドトレーナーとして、Fは、長年のマーケティング会社での経験を活かしチーフ・マーケティング・オフィサーとして、共同で事業を運営していくこととなっている。
在留資格「経営・管理」で行うことのできる業務
経営・管理に従事する者が、主たる活動としての純枠な経営・管理にあたる活動のほかに、その一環として従たる活動として行う現業に従事する活動は、「経営・管理」の在留資格に含まれます。
ただし、現業業務を恒常的に行う場合には、在留資格該当性が否定され得ます。
【 このような傾向にあります 】
- 飲食店経営者が経営の一環として調理業務を行う ⇨ OK
- ただし臨時的・一時的でなく例えばオーナシェフとして専ら調理業務に従事する場合 ⇨ NG
なお弊事務所の申請案件で、労働基準法遵守の観点からオーナー(経営・管理)以外に2名のキッチン従業者(正社員)とホール1名(パートでよい)を雇用するよう入管より指摘を受けたことがあります
- 病院を経営する医師が実際に診療を行う ⇨ OK
- 建築事務所を経営する建築士が実際に設計を行う ⇨ OK
- 英会話教室を経営する外国人が生徒へのレッスンにも従事すること ⇨ NG
「事業の管理に従事する」とは
具体的には、「部長・工場長・支店長など」の業務を実質的に従事すること、になります。
要件は以下になります。
① 3年以上の事業の経営または管理の実務経験を有すること
② 同等の職に就く日本人と同等の報酬が支払われること
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、「経営」をおこなっていいの?
企業の経営活動や管理活動は,自然科学若しくは人文科学の知識等を要する業務に従事する活動であることもあり,「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の対象となる活動と一部重複します。 しかし、入管法別表第1の2の表の「技術・人文知識・国際業務」の項の下欄は,本邦において行うことができる活動から「経営・管理」を除いています。 そこで、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では「経営・管理」業務を行えないのが原則です。 なお,企業の職員として「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で在留していた外国人が,昇進等により当該企業の経営者や管理者となったときは,直ちに「経営・管理」の在留資格に変更することまでは要しないこととし,現に有する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の在留期限の満了に併せて「経営・管理」の在留資格を決定しても差し支えません。 自ら起業した場合は、直ちに、在留資格変更申請をすべきでしょう。
第1 外国人による起業に関連した在留資格の整理
-1 総論
-2 経営者の基本的な在留資格「経営・管理」
-3 在留資格「経営・管理」利用促進のために起業“準備”活動を認めている在留資格や制度
.1 在留期間4月を指定される「経営・管理」
.2 外国人起業活動促進事業:「特定活動」(告示44号)
.3 未来創造人材制度(J-Find):「特定活動」(告示51号)
.4 日本の大学等を卒業した留学生による起業準備活動:「特定活動」(告示外)
-4 高度専門職の要件を満たす経営者の在留資格「高度経営・管理活動」
【コラム】過去の外国人企業に関する在留資格・制度の変遷
.1 国家戦略特区(東京都)
.2 外国人起業に関連した在留資格についての新しい動き※令和6年12月31日までの更新
第2 会社の設立に関する基礎知識
-1 総論
-2 定款と登記
.1 定款
.2 定款認証の特別処理
.3 テレビ電話による電子定款の認証
.4 登記
.5 外国人・海外居住者の方の商業・法人登記の手続
.6 電子定款の認証と設立登記のオンライン同時申請制度
-3 事業計画書
-4 外国人と銀行口座
-5 外為法上の対内直接投資(対日直接投資)に係る事前届出及び事後報告の義務
-6 その他類型別情報
.1 外国企業の日本支店を設立する場合
.2 一般社団法人
サイドメニュー
- Between Japan and Nepal
- Tokutei Ginou
- QandA
- Shop info
- English